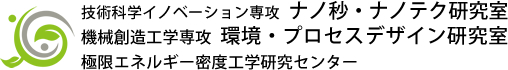国際連携
近年の先進的研究は単独のグループだけでは推進することが出来ません。特に、異分野で異なる考えを有する研究者との交流は非常に重要であると考え、国際的な連携体制を構築しています。本学は海外実務訓練制度(学部4年次に半年間実務訓練を行う制度)や、技術科学イノベーション専攻での海外派遣など多くの機会を利用し、相互の学生が交流しています。
アジア
モンゴル科学技術大学(モンゴル)
◆BAASANDASH Choijil 副学長
モンゴル国は現在、JICAの協力のもと、1000人の工科系人材を日本に留学させるというプログラム(JICA 工学系高等教育支援事業、モンゴルではMJEEDプログラム)を行っています。この事業においては、本学OBのロブサンニャム・ガントゥムル、前 教育・文化・科学大臣による多くのご尽力が有りました。我々の研究グループでは現在2名のモンゴル留学生を受け入れており、自然エネルギー利用技術について、BAASANDASH Choijil 副学長らと共に取り組んでいます。

モンゴル国 文部科学大臣、駐モンゴル日本国大使らとの面談
西安交通大学(中国)
◆Jian-Feng Yang教授
Yang先生が大阪大学留学時に私の一年上の先輩であった事から、公私共々大変お世話になっています。

(左) Yang先生、東北大学 林 先生と共に (右) 西安の風景
Wuhan University of Technology(中国)
◆Zhengyi FU教授、Hao Wang 教授
Fu教授の研究室とJSPS(日本学術振興会)による国際共同研究プログラム(A3 foresight Program) に採択され、強力な共同研究を推進しています。

Fu先生、Wang先生と共に
Inha大学 [仁荷大学校](韓国)
◆Sang Sub Kim教授
Kim教授は海外Coop教員として本研究室に2ヶ月滞在され、共同研究を行っています。今後は更に活発な研究室間交流が期待できます。

Inha大学を本研究室の学生が訪問したときの写真
Gyeongsang National Univ(韓国)
◆Dong Woo Shin教授、Jinsam CHOI教授ら多数との交流
Shin先生の研究室を出身の学生が、本研究グループの修士課程・博士課程に入学し、学位を取得しているなど、複数の教員と教育研究活動を共に行っています。
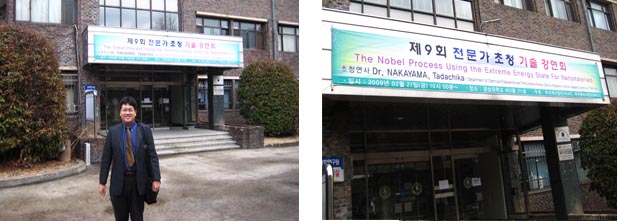
慶尚大学校での私の講演会時の写真

3ヶ月間共同研究のために本研究室に滞在された慶尚大学校Jinsam CHOI教授(右から二番目)の歓迎会の様子
SunMoon Univ(韓国)
◆Soo Wohn LEE教授
LEE先生の研究室を出身の学生が、本研究グループの修士課程、博士課程に入学し、学位を取得しているなど、教育研究活動を共に行っています。
Seoul National University of Technology(韓国)
◆Doh-Hyung Riu 准教授
Riu先生とは同じ研究室に所属した時期があり、共著論文を出したり、一緒に国際会議を運営したりと多様な共同研究を行っています。
Pusan National Univ(韓国)
◆Jeong Young-Keun教授
Jeong先生の研究室に本学の修士課程学生が2か月間留学しているほか、当該研究科との間で大学院博士課程学生の交流を積極的に進めています。特に、ハイブリッド材料の研究に関する共同研究がなされています。

Jeong Young-Keun先生と本研究室修士1年黒澤君と末松久幸教授
Hanyang Univ(韓国)
◆Choa Yong-Ho教授
10報以上の共著論文を出すなど、最も連携の強い研究室の一つです。

我々研究室の学生らと。左下がChoa先生
ホーチミン市工科大学(ベトナム)
◆電気電子工学科 学科長 Nguyen Huu Phuc 准教授
本学とのツイニングプログラムにより、ホーチミン市工科大学の電気電子工学科出身の学生が、本研究グループの学部生として入学するなど、教育研究活動を共に行っています。

Phuc先生、本学電気系正本先生と共に
ハノイ市工科大学(ベトナム)
◆Mai Thanh Tung教授
電気化学を利用した機能性薄膜に関する共同研究を行っています。また、Tung先生は本研究室に2010年に2ヶ月滞在され、共同研究を行われました。

Tung先生と小林事務補佐員の料理風景
ヨーロッパ
ヨーク大学(英国)
◆物理学科 Kevin O'Grady教授
相互に大学院生を受入れ、教育研究活動を共に行っています。

Kevin先生の研究グループのみんなと共に
ヨーク大学(英国)
◆電子工学科 Professor Dr. Atsufumi Hirohata先生
共著の学会発表を行っている他、国際共同研究プロジェクトを共同出願するなど、共同研究をしています。また、これまで過去6年間にわたり毎年1~3名の学生が5カ月間の海外実務訓練制度を用いて渡航しており、非常に活発に連携している研究室の一つです。

Hirohata先生と共に
ブリストル大学(英国)
◆生体分子を利用した機能性材料の創成プロセスの提案と実証
本学の学生を研究留学派遣するとともに、研究室を主宰しているReader, Dr. Simon(注; Readerは日本でいえば特に研究の業績に優れた教授または準教授相当)が2016年、2017年と連続して本学に2ヶ月滞在するなど最も活発な交流をしているグループの一つです。

Reader, Dr. Simonのグループの所に留学した学部4年の須藤君
オックスフォード大学 University of Oxford(英国)
◆ナノコンポジットセラミックスに関する共同研究を推進
本学の学生を研究留学派遣するとともに、ナノコンポジットセラミックスに関する研究活動を Professor Richard I Todd と共に行っています。また、我々のグループが仲介して多くの高専の学生が同先生の研究室を訪問し、世界最先端の知に触れています。
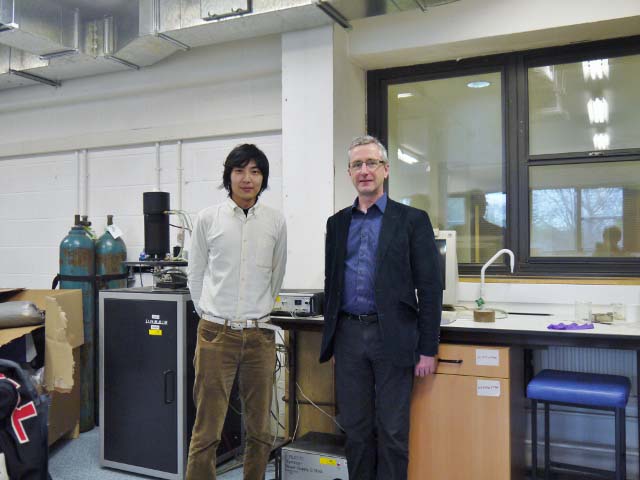
Todd教授と本研究室博士課程の藤原君
Aalto University School of Science and Technology(フィンランド)
◆Roman Nowak教授
2010年にはRoman Nowak教授、および同研究室の2名の教員が3か月間本研究室に滞在し研究を行ったほか、多数の共著論文を執筆しています。
なお、Aalto University School of Science and Technologyは旧名がヘルシンキ工科大学でフィンランドで最も有力な工科大学です。

Nowak先生歓迎会の様子(赤いネクタイがNowak先生)
Forschungszentrum Karlsruhe(ドイツ)
◆Horst Hahn教授
私の心の師匠。私が博士を取得するときの研究を指導してくださった教授の一人。ナノテクノロジー、材料開発の分野において、我々とかなり近い研究内容を行っており、相互に研究室訪問を繰り返し、いつもディスカッションしてくださっています。

Horst Hahn 教授
アメリカ
南フロリダ大学(米国)
◆Ashok Kumar教授
本研究室の博士修了学生が南フロリダ大の研究員として就職しており、更に、相互に大学院生を受入れなどの活動を通じて、活発な教育研究活動を共に行っています。

2009年に本学に留学したダニエル君とその様子を見に来たクマール教授らとの記念写真

南フロリダ大に半年間留学中の修士1年の吉村君のスナップ写真
その他
0RMIT University ロイヤルメルボルン工科大学 航空宇宙機械製造専攻(オーストラリア)
◆研究留学生を派遣
本研究室の大学院生を1ヶ月程度の短期研究留学させ、新規太陽電池の研究活動を共に行っています。
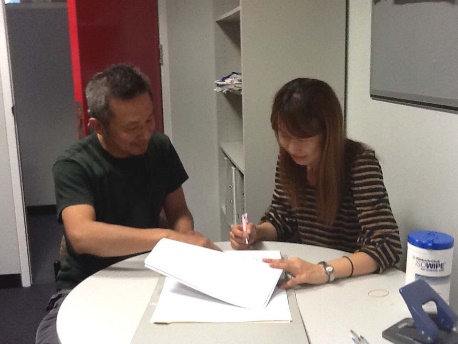
ディスカッションするRMIT大のTachibana教授と本研究室の李さん